 2月5日、金池の万寿寺さんで「涅槃図のお絵解き」が開催され、長勝寺の涅槃図も展示させて頂きました。
2月5日、金池の万寿寺さんで「涅槃図のお絵解き」が開催され、長勝寺の涅槃図も展示させて頂きました。
 こちらは万寿寺の佐々木道一老大師。今回の仏教講座という貴重なご縁を頂きました。
こちらは万寿寺の佐々木道一老大師。今回の仏教講座という貴重なご縁を頂きました。
お釈迦様のお亡くなりになるところを、あたかもそこに居合わせているかのような語りでお話しくださいました。
お釈迦様のご臨終のところでは思わずジーンときてしまいました。
お絵解きの中でもありましたが、お亡くなりになったお釈迦様を囲んで嘆き悲しむお弟子さま方のお姿を見ると、死に方とは生き方なんだなあとしみじみ感じました。死んだとき、こんなにも悲しんでくれる人がいるように生きなければ。。
反省(-_-;)
皆さんもお絵解きの機会がありましたら是非聞いてみて下さい。
おまけ
涅槃図には訳あって猫は描かれることが少ないそうですが、こちらのネコさんはそんなことは知らないニャンと、和尚さんたちに遊んでもらっていました。
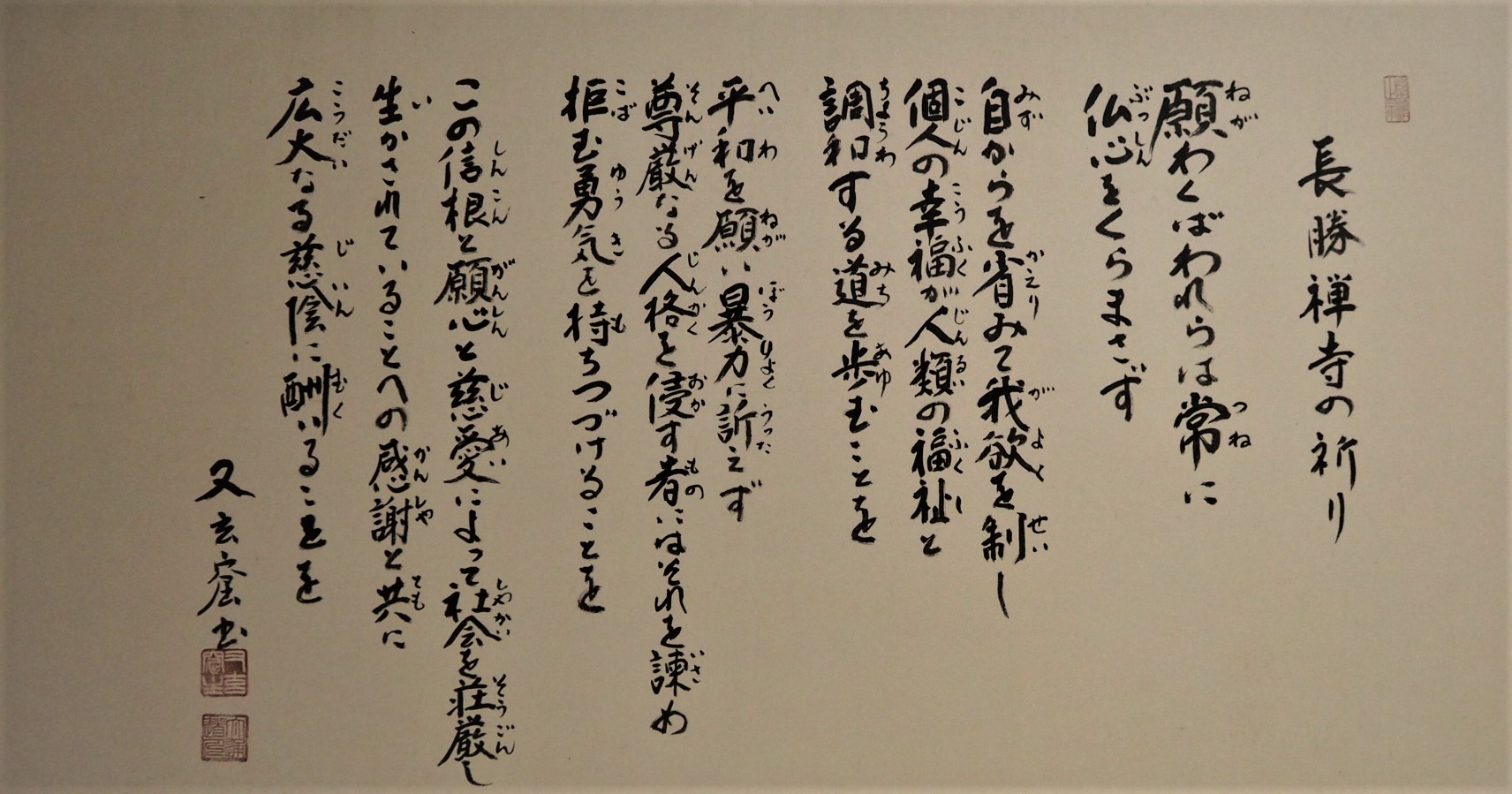


 直角三角形とレーザーを両方使って確認しています。
直角三角形とレーザーを両方使って確認しています。




















